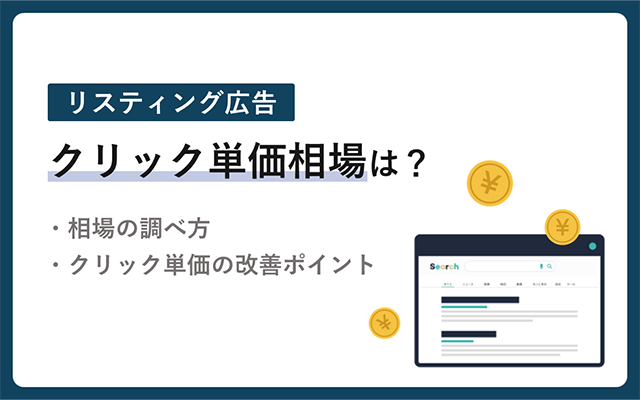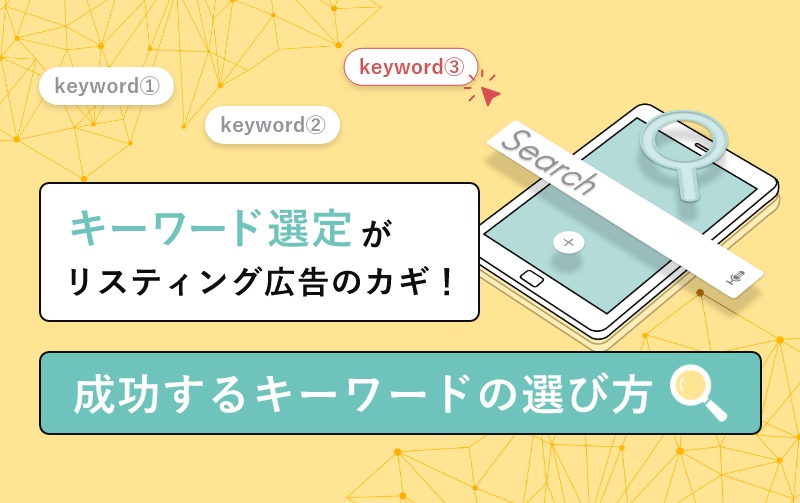成果を出せないオウンドメディア担当者に向けた8つの運用ポイント
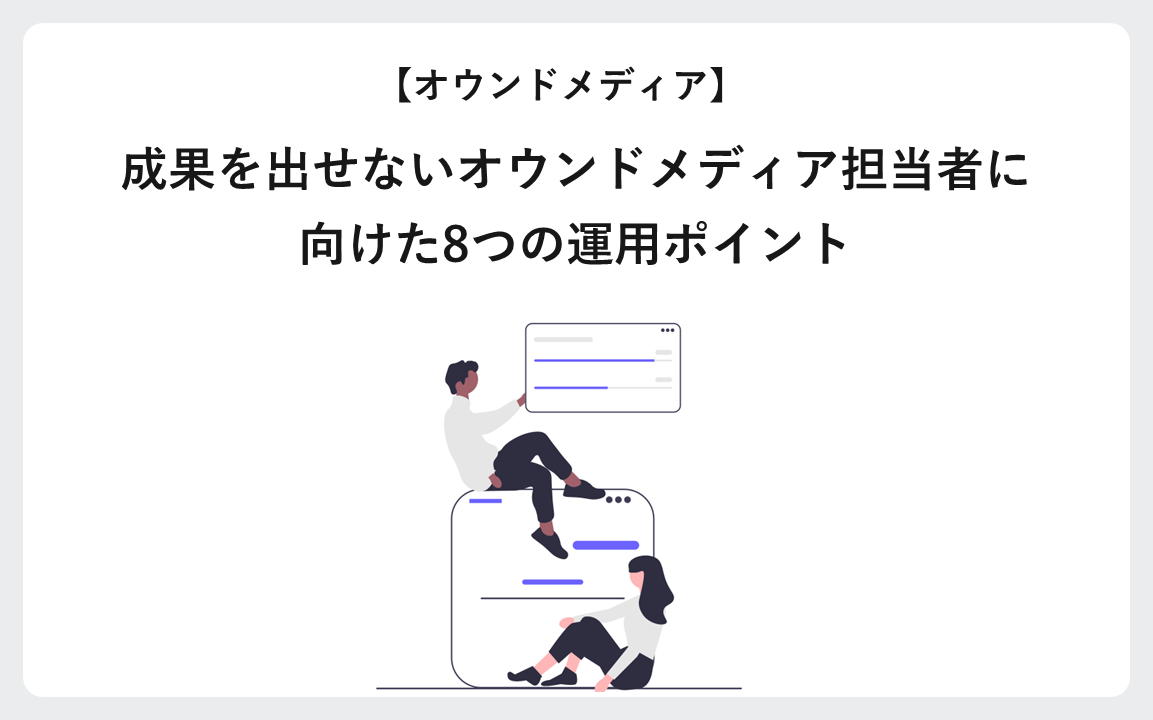
オウンドメディアは、顧客とコミュニケーションを取れる重要な接点であり、多くの企業が運用しています。
しかし、自社にオウンドメディアのノウハウがないため、なかなか成果が出せないと悩む企業担当者は少なくありません。
そこで本記事では、オウンドメディアの運用において重要な心構えや運用ポイントを解説します。オウンドメディアの運用で行き詰っている担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、打開策を見つけてください。
参考記事
リスティング広告を世界標準のAIで改善させる
マーケティング活動で重要なリスティング広告。現状実績を改善し、さらに成果を伸ばすことに苦戦しているマーケティング担当者は多いです。弊社ではリスティングAIを活用した、まったく新しいご提案が可能です。
- リスティング広告のコンバージョン数を確実に改善させたい
- 人の手で実績を改善し続けるのが困難
- リスティング広告のプロフェッショナルに課題解決の相談をしたい
こちらから
目次
1.オウンドメディアの運用で大切な1つの心構え
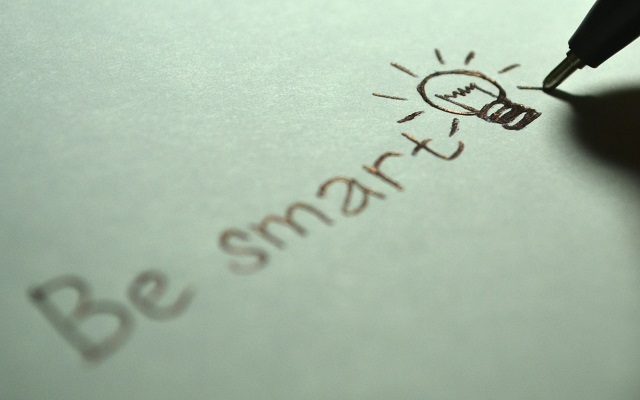
オウンドメディアの種類は、ブログやSNS、ニュースレターなど多岐にわたります。
どのチャネルを選ぶにしても、オウンドメディアの運用ではコンテンツ発信が重要です。それでは、どのようなコンテンツを発信すればよいのでしょうか。
1997年、アメリカの社会学者マイケル・ゴールドハーバー氏が「アテンション・エコノミー」という概念を提唱しました。
アテンション・エコノミーとは:
無料のコンテンツやオンラインサービスが普及する現代において、人々の関心や注目が貨幣のように経済的価値を持つ状況のこと。
アテンション・エコノミーにおいては、人々の時間は貴重な価値を持ちます。
ユーザーは貴重な時間を割いて、無料のコンテンツを読むからこそ、価値のあるコンテンツを提供しなければならない。
価値のあるコンテンツとは、主に以下のものを示します。
- ユーザーの悩みや課題を解決する
- 教育的
- 面白い
多額の予算を投下したり、優れた戦略を練ったりしても、コンテンツの質が低ければオウンドメディアの運用は成功しません。オウンドメディアの運用では、常にユーザーに価値あるコンテンツを提供することを心がけましょう。
2.オウンドメディアで成果を出す運用ポイント8選

オウンドメディアの運用を誤れば、期待した成果にはつながらない懸念があります。ここからは、オウンドメディアの運用ポイントを8つに分けて解説します。
2-1.目的を明確にする
オウンドメディアは、すでに多くの企業が参入しているレッドオーシャンです。また、成果が出るまでに半年以上の時間がかかる点も考慮すると、明確な目的設定が必要となります。
オウンドメディア運用における主な目的は、以下の4つです。
- 新規顧客の創出(認知度向上)
- 信頼関係の構築(購買意欲の醸成)
- ブランディング
- 採用
設定する目的によって、最適なコンテンツは異なります。
【例】
新規顧客の創出が目的なら、課題や悩みの顕在層にアプローチできるSEO記事が有効。
一方、採用が目的ならSEO記事ではなく、社員インタビューや企業ミッションなどが最適です。企業の経営目標や全体のマーケティングゴールのなかから、オウンドメディアが貢献できる部分を特定し、目的を設定しましょう。
オウンドメディアの目的については、下記記事で詳しく解説しているので、ぜひこちらも参考にしてください。
参考記事
2-1.目的を明確にする
オウンドメディアの目的を設定したら、目的を達成するためのKPIを設定します。
オウンドメディアは成果が出るまでに時間がかかる中長期の施策のため、フェーズ別にKPIを設定するのが有効。
- SEO対策の場合
運用初期は流入数が少なくコンバージョンが期待できないことから、コンテンツ数やPV数をKPIにし、安定した流入が見込めた段階でコンバージョンをKPIに設定。
- Instagram経由で売り上げアップが目的の場合
まずはフォロワー数やインプレッション数をKPIにし、フォロワー数が増えたらインプレッションやサイトへの流入数などをKPIに設定。
フェーズ別に最適なKPIを設定すれば、成果の進捗を可視化できるため、社内からの協力も得られるでしょう。
2-3.顧客理解を深める
先にお伝えした通り、オウンドメディアの運用では顧客にとって価値ある情報を提供しなければ成功しません。
顧客理解を深めることで、顧客の抱える悩みや課題が判明し、顧客にとって価値あるコンテンツが判明する。
顧客理解を深めるために有効な手法は以下の通りです。
- ユーザーインタビュー
- 営業やカスタマーサクセスなど顧客接点のある部署にヒアリング
- 自社/競合他社の導入事例の分析
- 口コミ評価の確認
- SNSで自社/競合他社のチェック
- アンケート調査
手間がかかる工程ではありますが、多くの一次情報を集めて、顧客への解像度を高めることで、質の高い企画出しやコンテンツ作成が可能となります。
なお、一次情報をもとにペルソナを作成し、メンバーと共有すると、全員が同じ顧客像を持ってオウンドメディアの運用に取り組めるようになります。
また、自社認知の拡大や市場の変化により、ペルソナのニーズや課題は変化するため、定期的にペルソナの見直しをしましょう。
参考記事
2-4.適切なキーワード選定をする
オウンドメディアでSEO対策をする場合、キーワード選定が戦略の軸となります。
キーワードは検索ボリュームに応じて、以下3つに分類できます。
- ビッグキーワード:1万回以上
- ミドルキーワード:1,000~1万回未満
- スモールキーワード:1,000回未満
検索ボリュームは、Google アナリティクスや有料ツールで調査できます。
オウンドメディアの運用開始初期は、ミドル・スモールキーワードを中心に記事制作をするのがおすすめ。
ビッグキーワードで記事制作をしても、内部リンク数やドメインパワーが不足した状態だと、上位表示は難しいでしょう。その他にも、コンバージョン率の高いキーワードやキーワードごとの検索意図の把握などを行わなければいけません。
SEOのキーワード選定の方法については、下記記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。
参考記事
2-5.戦略を設計する
単に良質なコンテンツを発信するだけでは、成果につながらないどころか、施策中止の懸念が生じます。社内の理解を得るためにも、早い段階で効果を得られるように、戦略を設計しましょう。
具体的には、受注に近いコンテンツから作成するのが有効。
例えば、オウンドメディアの運用で自社認知度を高められたとしましょう。しかし、自社認知度が拡大しても、実績ページや導入事例などを作成していなければ、受注や商談、コンバージョンにはつながりません。
まずは製品紹介や会社の実績、メンバー紹介、導入事例などの受注やコンバージョンへの貢献度が高いコンテンツから作成しましょう。
受注に近いコンテンツの作成ができたら、オウンドメディアの運用に取り組みます。オウンドメディアの最大の強みは、多くの潜在層や顕在層にアプローチし、自社認知度を高められる点です。
オウンドメディアの運用で認知拡大を達成できれば、オウンドメディアに訪問したユーザーはコンバージョンをし、商品購入や商談申し込みなどをしてくれるでしょう。
オウンドメディアに流入がありながらも、目的を達成できていない場合は、受注やコンバージョンに近いコンテンツの作成や改善をすることを推奨します。
2-6.インソースとアウトソースを使い分ける
オウンドメディア運用で成功するためには、継続的にコンテンツを発信しなければいけません。
成果が出ないためにオウンドメディアの運用を中止する企業は多いため、継続できるだけで競合と差をつけられます。
オウンドメディアを継続するためには、コンテンツの制作体制を整えることが重要。
理想は、インハウス(自社内)でコンテンツを作成することですが、人的リソースが少ない場合はアウトソースも検討しましょう。
アウトソースを活用する際のポイントは2つあります。
- 構成案の作成は自社で行うこと
構成案は、コンテンツの質に大きな影響を及ぼす。完全に外部ライターに任せると、仕上がりイメージとかけ離れた記事になる懸念もあるため、構成案は自社で作成する、もしくは一度構成案の確認をしてから記事執筆を依頼するのがよい。
- BtoB企業のアウトソース活用
BtoB領域は専門性が高いため、BtoC領域と比較すると最適な制作会社やライターを見つけるのは難しい。
↓
可能な限り、インハウスでコンテンツ作成をすることを推奨するが、人的リソースが不足する場合は、経験のあるライターを採用したり、コンテンツ作成講座の依頼をしたりするのがおすすめ。
アウトソースを利用する際は、顧客ニーズを的確にとらえ、ユーザーに刺さるコンテンツを作成できる体制を整えましょう。
2-7.トリプルメディアを活用する
トリプルメディアとは、以下3つのメディアの総称です。
| オウンドメディア | ペイドメディア | アーンドメディア | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 自社で運用するメディア | 費用を支払って広告掲載するメディア | ユーザーや消費者などが発信するメディアのこと |
| 例 | ・ブログ ・ニュースレター ・SNS |
・リスティング広告 ・ディスプレイ広告 ・SNS広告 |
・口コミ ・SNSでの投稿 |
| アプローチできる層 | 潜在層 | 顕在層 | 潜在層 |
3つのメディアを組み合わせることで、効率よく目標達成できます。
【例】
SEO対策とリスティング広告を併用すれば、SEOで効果が出るまでの期間、リスティング広告が集客に貢献できる。
もしくは、オウンドメディアで作成したコンテンツをSNSでシェアするのではなく、予算を投下しインフルエンサーにシェアしてもらえば、拡散力も期待できるでしょう。
このように運用初期の集客につながりにくいフェーズにこそ、複数メディアの活用がおすすめです。
2-8.分析と改善を繰り返す
オウンドメディアのコンテンツは公開して終わりではありません。各チャネルで公開したコンテンツのパフォーマンスを分析し、必要に応じて改善に取り組みましょう。
【例】
コンバージョン率が低い場合、CTAの位置や文言などの改善が有効。
コンテンツを発信し、データが蓄積されたら、分析と仮説立てをしましょう。1つずつ仮説を検証し、改善を繰り返すことで、大きな成果へとつながります。
3.オウンドメディアの運用を諦めるのも一つの手

オウンドメディアの運用で、どうしても成果が出ないときは、オウンドメディアが最適な施策ではない可能性があります。
【例】
- 顧客がWebで情報収集をしていない場合、オウンドメディアを運用しても大きな成果にはつながらない。
- リアルマーケティング主体の会社が、いきなりSEO対策やSNSアカウントなどのオウンドメディアを運用するのもおすすめできない。
オウンドメディアで成果を出すためには、SEOやアクセス解析をはじめとした多くのWebマーケティングスキルが求められます。社内にWebマーケティング人材がいない、もしくはマーケティング部が小さい場合は、大きな負担となるでしょう。
また、オウンドメディアで成果が出るには一定の期間が必要なため、社内の反対が生じる懸念もあります。オウンドメディアは流行りの施策のため、多くの企業が取り組んでいるのは事実ですが、必ずしも自社に最適な施策とは限りません。
オウンドメディアよりも、検討段階の見込み客に直接アプローチできるリスティング広告やセミナーなどの施策の方が有効な可能性はあります。
以下のいずれかに該当する場合は、オウンドメディア以外の施策を検討してみましょう。
- 商材に関する検索ボリュームが少ない
- ターゲットがWebで情報収集をしない
- オウンドメディア運用に必要なリソースを確保できない
- 類似製品がない新しい製品のプロモーション
このような状況では、必ずしもオウンドメディアが必要とは限りません。オウンドメディアが最適かどうか判断するには、顧客の購入プロセスを可視化したカスタマージャーニーの作成が有効です。
カスタマージャーニーを作成することで、顧客とのタッチポイントを洗い出し、最適なチャネルで施策を推進できるようになります。
4.まとめ
オウンドメディアの運用ポイントは多々ありますが、最も重要なのはコンテンツを通してユーザーに価値提供することです。ユーザーに価値を提供し続けることで、信頼関係が構築でき、新規顧客の創出やブランディングなどの成果を見込めます。
また、自社にオウンドメディアが適しているかどうかの判断も必要です。多くの企業がオウンドメディアを運用している一方、リスティング広告やオフラインでの施策が最適なケースもあります。
あくまでもオウンドメディアはマーケティング施策の一部であり、オウンドメディアだけにこだわる必要はありません。
参考記事
リスティング広告を世界標準のAIで改善させる
マーケティング活動で重要なリスティング広告。現状実績を改善し、さらに成果を伸ばすことに苦戦しているマーケティング担当者は多いです。弊社ではリスティングAIを活用した、まったく新しいご提案が可能です。
- リスティング広告のコンバージョン数を確実に改善させたい
- 人の手で実績を改善し続けるのが困難
- リスティング広告のプロフェッショナルに課題解決の相談をしたい
こちらから

アドフレックス編集部
アドフレックス・コミュニケーションズ公式アカウントです。
アドフレックス・コミュニケーションズ公式アカウントです。