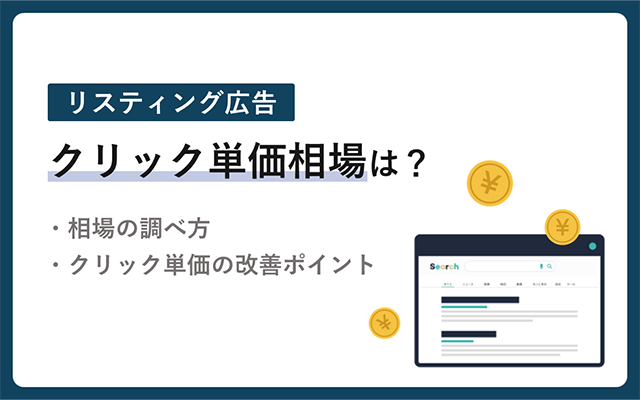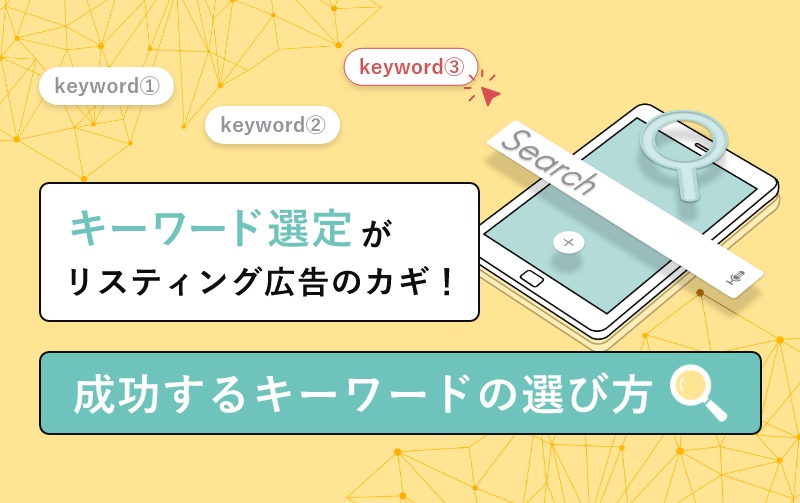【動画広告の基礎知識】広告や配信先の種類、効果測定方法までまとめて解説
近年、インターネット広告費に占める動画広告比率が急成長をしています。2021年2月に電通グループが発表した調査「2020年 日本の広告費」によると、前年比121.3%の3,862億円の伸長と、インターネット広告費全体の22%を動画広告が占めるまでになっています。
動画広告にはインストリーム広告やインバナー広告など、さまざまな種類があります。配信先についても、YouTubeをはじめ、さまざまなWebサイトやSNSが用意されています。
本記事では、 動画広告の概要やメリット、目的別の効果測定までを網羅。新たな施策を検討される際などの参考にしてみてください。
リスティング広告を世界標準のAIで改善させる
マーケティング活動で重要なリスティング広告。現状実績を改善し、さらに成果を伸ばすことに苦戦しているマーケティング担当者は多いです。弊社ではリスティングAIを活用した、まったく新しいご提案が可能です。
- リスティング広告のコンバージョン数を確実に改善させたい
- 人の手で実績を改善し続けるのが困難
- リスティング広告のプロフェッショナルに課題解決の相談をしたい
こちらから
目次
1.動画広告とは
動画広告とは:
広告に動画を使用したインターネット広告全般のこと。
かつてインターネット広告といえば、テキストや静止画を使ったものが主流でした。その背景には、動画はデータ容量が重いため、再生の途中で止まったり、途切れてしまうことが多い、といった課題がありました。
しかし、最近では通信環境も向上し、Wi-Fiや4G(第4世代移動通信システム)の普及、さらには5G(第5世代移動通信システム)がスタートしたことで、どのデバイスからでも快適に動画が楽しめるようになりました。それに伴い動画広告市場も大きく成長。商品やサービスを音と映像で訴求できる手法として、注目を集めています。
国内電通グループ4社(CCI/D2C/電通/電通デジタル)の調査によると、2021年の動画広告は前年比110.4%増の4,263億円と予想されています。動画広告市場は、今後も成長が見込まれます。
2.動画広告のメリット
画像やテキストを使った静的な広告と比べ、動画広告には多くのメリットがあります。ここでは、動画広告のメリットを項目別にご紹介します。
2-1.映像と音で多くの情報を伝えられる
『照明学会編:屋内照明のガイド』(電気書院)によると、人間は視覚(87%)と聴覚(7%)だけで、受ける情報の9割以上を占めるそうです。
映像と音声、音楽で構成される動画広告は、視覚と聴覚に訴えかけることでより効果的に、印象に残る内容を伝えることができます。
2-2.静止画広告よりもストーリーを持たせやすい
米スタンフォード大学のJennifer Aaker教授は、事実や数字の羅列よりも、ストーリーがあることで最大22倍も人の記憶に残る、と発表しています。
動画広告の最大の魅力は、なんといってもストーリーの伝えやすさ。記憶に残る広告を配信することでブランディングなどにも有効です。
2-3.拡散力がある
効果的な動画広告は、視聴者に大きなインパクトを与えることができます。話題性のある動画広告はSNSやブログなどで拡散されやすく、大きなマーケティング効果が期待できます。
3.動画広告の種類と特徴

動画広告は動画コンテンツ内で表示されるインストリーム広告と、別枠で表示されるアウトストリーム広告に大きく分類されます。
3-1.インストリーム広告
YouTubeなどに代表される動画コンテンツの再生前後や再生途中に流れる動画広告を「インストリーム広告」といいます。
インストリーム広告には、決められた秒数の経過後に広告再生をスキップできる「スキッパブル広告」と、広告のスキップはできない「ノンスキッパブル広告」の2種類があります。
また、動画コンテンツの再生前に流れるものは「プレロール広告」、動画コンテンツの再生途中に流れるものは「ミッドロール広告」や「バンパー広告」、動画コンテンツの再生後に流れるものは「ポストロール広告」といいます。
テレビCMと同様に、動画コンテンツの画面内で再生されるインストリーム広告は、印象に残りやすいという特徴があります。また、動画のジャンルとマッチした広告が入れられるので、そのジャンルに興味を持つターゲットに絞った広告配信ができ ます。
3-2.インバナー広告
バナー広告の掲載枠で配信される動画広告が、「インバナー広告」です。代表的なものに、Yahoo! JAPANのトップページ上に表示されるものがあります。
インバナー広告は、検索エンジンなどにも表示されるため、動画をあまり視聴しないユーザー層にもアプローチできる特徴があります。
3-3.インリード広告
TwitterやFacebookなどのSNSや、Webサイト上のコンテンツやタイムラインの途中で再生される動画広告が「インリード広告」です。
ページのスクロール途中に広告再生がスタートするので、最初から見てもらえるというメリットがあります。そのため、特にストーリー性のあるものと相性が良いという特徴があります。
また、コンテンツと同じ枠に表示されるので、静止画のバナー広告よりも視認性が高くなります。
3-4.インフィード広告
「インフィード広告」は、インリード広告と同じくSNSのタイムラインやWebサイトのコンテンツの途中に再生される動画広告です。
インリード広告は動画広告のみを、インフィード広告は動画広告以外に静止画広告も含まれるという違いがあります。
ページのスクロール中に再生されることから、スクロールを多用するスマートフォンと相性が良いです。
4.動画広告の主な配信先

動画広告の成長に合わせて、配信先も増えています。主要プラットフォーム8つをご紹介します。
4-1.YouTube
国内だけで月間アクティブユーザー数6,500万人以上(2020年9月現在)を抱える、世界最大の動画配信プラットフォームがYouTubeです。視聴者層も10代以下から50代以上までと幅広い層にアプローチできるのが特徴です。ターゲティングを行うことで、狙っているユーザー層に向けて的確にアプローチを行うことができます。
動画コンテンツの視聴を目的としているので、動画広告も違和感なく視聴してもらえるという強みがあります。最近では、動画コンテンツの再生前、再生中、再生後に表示される6秒以内のバンパー広告も増えています。
参考記事
リスティング広告を世界標準のAIで改善させる
マーケティング活動で重要なリスティング広告。現状実績を改善し、さらに成果を伸ばすことに苦戦しているマーケティング担当者は多いです。弊社ではリスティングAIを活用した、まったく新しいご提案が可能です。
- リスティング広告のコンバージョン数を確実に改善させたい
- 人の手で実績を改善し続けるのが困難
- リスティング広告のプロフェッショナルに課題解決の相談をしたい
こちらから

アドフレックス編集部
アドフレックス・コミュニケーションズ公式アカウントです。
アドフレックス・コミュニケーションズ公式アカウントです。