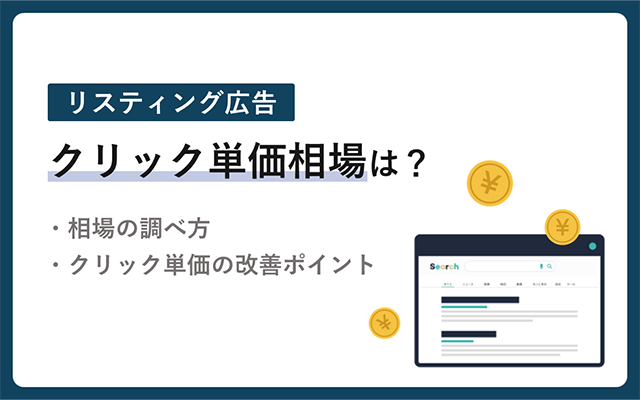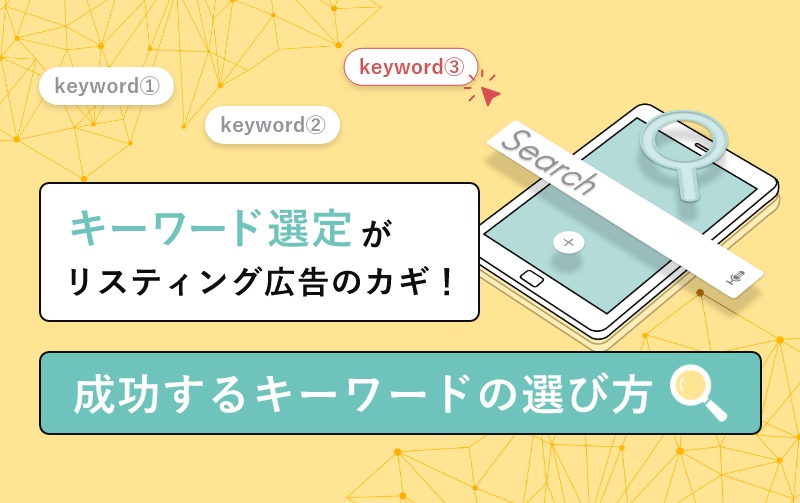オウンドメディアの4つの目的!始め方やKPIの設定方法も解説

オウンドメディアの運用を検討しているものの、具体的な目的やKPIの設定が分からないとお悩みではないでしょうか。
オウンドメディアを運用している競合他社は多く、成果が出るまでに時間がかかるからこそ、明確な目的設定が必要です。また、目的に応じて発信するコンテンツも変わります。
本記事では、オウンドメディア運営初心者でも適切な目的設定ができるように、4つの目的とKPIの設定方法、始め方の手順を解説します。
リスティング広告を世界標準のAIで改善させる
マーケティング活動で重要なリスティング広告。現状実績を改善し、さらに成果を伸ばすことに苦戦しているマーケティング担当者は多いです。弊社ではリスティングAIを活用した、まったく新しいご提案が可能です。
- リスティング広告のコンバージョン数を確実に改善させたい
- 人の手で実績を改善し続けるのが困難
- リスティング広告のプロフェッショナルに課題解決の相談をしたい
こちらから
目次
1.そもそもオウンドメディアとは

オウンドメディアとは:
自社が運用するメディアのこと。オウンドメディア=サイトやブログと考えられがちだが、SNSやニュースレター、店舗などもオウンドメディアに該当する。
オウンドメディアの特徴として、発信する情報を自社でコントロールできるため、自社や製品の魅力を効果的に伝えられる点が挙げられます。
一方、SEO対策をはじめとした各施策で成果を出すためには、少なくとも半年は継続しなければいけません。
2.オウンドメディアを運用する4つの目的
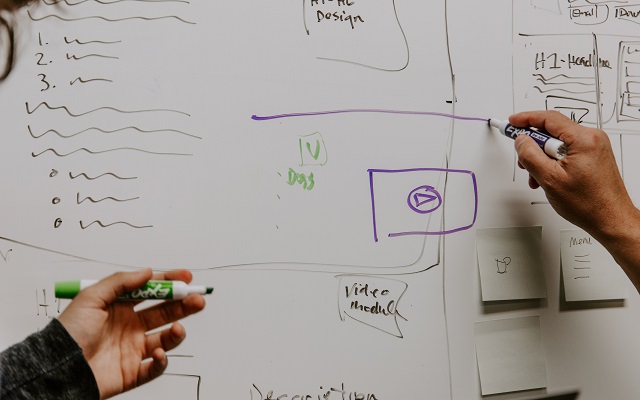
オウンドメディアを運用する目的は以下の4つです。
- 新規顧客の創出
- 信頼関係の構築
- ブランディング
- 採用
4つの目的の詳細について見ていきましょう。
2-1.新規顧客の創出
【この目的に適した主なコンテンツ】
- SEO記事
- SNS
オウンドメディアは、自社の認知度を拡大して、新規顧客との接点を構築するのを得意とします。
【例】
オウンドメディアでSEO対策を実施すれば、課題や悩みの解決法を探すユーザーに向けて、問題解決の糸口となる価値ある情報を発信でき、最終的には自社コンテンツへの誘導をうながせる。
インターネットの登場やスマートフォンの普及により、顧客の購買行動は大きく変化しました。従来、消費者は営業や広告などで接点を持った企業の商材を購買していましたが、見方を変えれば、受動的な購買プロセスでした。
しかし、インターネットの普及により、消費者はWebの情報を参考にし、自身の抱える課題の解決策を能動的に選べる時代になったわけです。
消費者が企業や情報を選べるようになったからこそ、有益なコンテンツを発信し、消費者に選んでもらうオウンドメディアの重要性が増している。
2-2.顧客との信頼関係の構築
【この目的に適した主なコンテンツ】
- SEO記事
- SNS
- ニュースレター
エデルマン・ジャパン株式会社が実施した消費者意識調査「2019 エデルマン・トラストバロメーター スペシャルレポート:ブランドは信頼に値するのか」によると、国内消費者の70%がブランドに対する信頼が購買決定に影響を与えると回答しています。
この調査結果からも分かる通り、企業のマーケティング活動において消費者の信頼を得ることは非常に重要となる。
企業が信頼を獲得するためには、消費者との丁寧なコミュニケーションが欠かせません。同調査では、「インフルエンサーや知り合いからのご紹介で認知を獲得したのち、オウンドメディアで接点を作ることで、74%の消費者がブランドを信頼する」と明らかになっています。
また、オウンドメディアから信頼関係を構築することも可能です。
【例】
ブログ記事でユーザーに価値ある情報を提供し続けると、徐々に信頼関係の構築ができ、ユーザーは購入や問い合わせなどのアクションを起こしやすくなる。
もしくはSNSで、顧客からの問い合わせや悩みに丁寧に回答するのも、信頼関係の構築に有効です。
2-3.ブランディング
【この目的に適した主なコンテンツ】
- 企業ストーリー
- 製品開発秘話
テクノロジーの発展により、製品やサービスの模倣が容易になった現代、消費者はブランドで購買するかどうか決定します。
【例】
多くのスマートフォンブランドがあるなか、Appleが多くのファンに選ばれる理由、多くのコーヒーチェーン店があるなかスターバックスが選ばれる理由はブランドにある。
ブランディングを行うことで、製品や機能で差別化が難しい現代において、企業は選ばれるブランドを構築できるのです。
オウンドメディアは、自社が発信したい情報を発信できるため、ブランディングに有効なチャネルだと言えるでしょう。
ブランディングで重要なポイントは、あらゆるチャネルで一貫性のある統一したメッセージを発信すること。
【例】
- ダイキン工業株式会社
自社を「空気で答えを出す会社」と定義し、テレビ広告やオウンドメディアで統一したメッセージを発信したことでブランディングに成功。
【例】
- HubSpot
インバウンドマーケティングを提唱し、あらゆるテーマの記事で顧客理解やインバウンドの思想の重要性を説くことで、インバウンドマーケティング=HubSpotと顧客に想起してもらえるようになった。
多くの顧客・潜在顧客にリーチできるオウンドメディアは、ブランディングにおける重要なチャネルの一つです。
2-4.採用
【この目的に適した主なコンテンツ】
- 企業ストーリー
- 社員インタビュー
オウンドメディアの運用は、優秀な人材の獲得にも期待できます。「人事のミカタの調査」によれば、転職活動者の9割が企業オフィシャルサイトから情報収集をすると発表しています。
つまり、オウンドメディアは求職者との重要な接点でもあるのです。
【例】
株式会社ベイジは、社員による日報や濃密な記事をオウンドメディアで公開し続けた結果、外部メディアやエージェントに頼らずに年間14人(応募者総数136人)の採用に成功している。
特に採用活動に大きな予算をかけられない企業にとっては、安価で始められるオウンドメディアは有効な採用チャネルとなります。
3.オウンドメディアの始め方

オウンドメディアの目的が分かったところで、始め方を解説します。
3-1.STEP1:目的設定
オウンドメディアの運用は中長期の施策となるため、軸となる目的を設定しなければいけません。
【例】
新規顧客の創出とブランディングでは、最適なチャネルやメッセージが異なる。
自社が抱える課題を洗い出し、オウンドメディアで解決できる課題を選定しましょう。
3-2.STEP2:チーム編成
解決する課題や目標が決まったら、チーム編成をしましょう。マーケティング部のメンバーだけで編成されるのが一般的ですが、営業やカスタマーサクセスなどの顧客と直接接点を持つメンバーを入れるのがおすすめです。
顧客と直接接点を持つメンバーを加えれば、実在する顧客が抱える課題や悩みを明確化でき、ユーザー視点でのコンテンツ制作ができるようになる。
顧客にとって価値ある情報を発信するためにも、部門横断型のチーム編成を目指しましょう。
3-3.STEP3:ペルソナ設定
顧客理解を深めるためには、ペルソナ設定が有効です。
ペルソナとは:
商品やサービスを利用する典型的なユーザー像。ペルソナ作成の際は、下記手法で顧客に関する一次情報を集めるのが有効。
- ユーザーヒアリング
- アンケート調査
- 導入事例を分析
- 商談履歴を分析
- 商談に同席
一次情報を用いることで、実在する顧客に極めて近いペルソナを作成できるようになります。また、メンバーの顧客に対する解像度が上がるため、質の高いコンテンツアイデアの創出に期待できます。
参考記事
3-4.STEP4:チャネルの決定
オウンドメディアと一口に言っても、ブログやSNS、ニュースレターなどさまざまなチャネルがあります。
オウンドメディアの目的やターゲットの属性、自社/競合状況などを考慮したうえで、最適なチャネルを選定するようにしましょう。
【例】
オウンドメディア運用の目的が新規顧客の創出であり、競合他社がWeb広告を中心に顕在層の獲得をしている場合、オウンドメディアでのSEO対策にチャンスがある。
重要なポイントは、各チャネルの特性を理解したうえで、戦略や商材とマッチしたチャネルを選定することです。
3-5.STEP5:運用開始
ここまでの手順でオウンドメディアを始める準備ができたので、実際にコンテンツを作成して、運用を開始します。しかし、単に顧客ニーズを満たすコンテンツ作成をするだけでは、目標は達成できません。
【例】
新規顧客の創出を目的とした場合、KPI(Key Performance Indicators)は問い合わせや商談数などに設定できる。
SEO記事は、あくまでも認知のきっかけにすぎません。ユーザーは、検索結果よりあなたのオウンドメディアを発見し、いくつかの記事を読んで興味関心を高め、詳細を知ろうとホワイトペーパーや事例をダウンロードするわけです。
つまり、コンバージョン率や受注率などの目的達成に直接貢献するコンテンツを作成しなければいけません。
目的達成に近いコンテンツを作成しないでオウンドメディア運営をした場合、SEO対策で多くの記事を上位表示できたとしても、コンバージョンにつながる導線コンテンツがないため、目的達成はできません。
また、ブログ記事やSNSなど認知度向上を担うコンテンツ施策は、成果が出るまでに時間がかかります。成果の測定も難しいため、オウンドメディア運用が中止となる懸念も指摘されています。
そのため、短期的に成果をあげられるコンバージョンに近いコンテンツから作成しましょう。
SEO対策で新規顧客の集客を狙うなら、ダウンロードコンテンツやサービスの詳細ページなどコンバージョンに直結するコンテンツ作成に注力してから、通常の記事制作に移行するといいでしょう。
3-6.STEP6:高速でPDCAを回す
オウンドメディアの運用で成果を出す近道は、地道にコンテンツ作成を継続することです。実際にオウンドメディアの運営をすると分かりますが、すぐに成果が出ることはめったにありません。
地道にコンテンツを発信し、蓄積したデータの分析をもとに、改善を続けることで成果が生まれる。
なかなか成果の兆しが見えないゆえに、多くの企業が途中で運用を中止するため、長期的に運用さえできれば大きく差をつけられるでしょう。
また、失敗を恐れずにさまざまな施策に取り組むことも成功の秘訣です。特にオウンドメディア運用の初期から中期にかけては、ノウハウやデータを蓄積するために、さまざまな施策に取り組みましょう。
4.オウンドメディアのKPIはフェーズごとに変える

オウンドメディアのKPI設定で悩む担当者は少なくありません。結論からお伝えすると、オウンドメディアのKPIはフェーズごとに変えるのがおすすめです。
例えば、運用初期段階にコンバージョン率をKPIに設定したとしましょう。しかし、オウンドメディア運用初期は流入数が少ないため、コンバージョンは見込めません。そこで運用初期は、PV数やセッション数/時間などをKPIに設定するといいでしょう。
フェーズ別の主なKPIは以下の通りです。
- 運用開始~半年:コンテンツ本数、PV数、セッション数/時間
- 半年~1年半:PV数、訪問者数、滞在時間、回遊率、熟読率
- 1年~2年:問い合わせ数、総客数、製品の購入数
上記KPIは参考程度にとどめ、実際の運用状況を見ながら、最適なKPIを設定するようにしましょう。
最終的には、オウンドメディアの売り上げや問い合わせ数など、KGI(Key Goal Indicator)から逆算したKPI(Key Performance Indicators)を設定する必要があります。
【例】
売り上げをKGIに設定した場合のKPI
売り上げ (KGI) = (サイト訪問者数 × 購入率) × 顧客単価
上記は売り上げをKGIに設定したケースですが、さらに深掘りすれば、サイト訪問者数は「新規訪問者」と「リピーター」に分けられるわけです。Google アナリティクスの詳細データも参考にして、KPIを深掘りしていきましょう。
参考記事
5.オウンドメディアの運用は他のチャネルと組み合わせるのが有効

オウンドメディアの運用が軌道に乗ったら、アーンドメディアやペイドメディアなど他のチャネルの追加を検討しましょう。
オウンドメディアでアプローチできるのは、「潜在層(悩みを持つ可能性がある層)」と「準顕在層(悩みはあるが解決策はまだ求めていない)」です。
そこで顕在層にアプローチできるチャネルも追加すると、効率よくリードを獲得できます。
顕在層にアプローチできるチャネルは主に、リスティング広告や導入事例の配布、メディアの露出などがある。
特にリスティング広告は、オウンドメディアとの相性が良いので検討してみてください。
リスティング広告は、多くの顕在層にアプローチできるため、効果の即効性に期待できる。
オウンドメディアとリスティング広告を併用することで、オウンドメディアの効果が現れるまでのタイムラグをカバーできるのです。
まずはオウンドメディアとリスティング広告を同時運用し、オウンドメディアのパフォーマンスが安定し始めたら、顕在層にアプローチできるチャネルの追加を検討しましょう。
6.まとめ
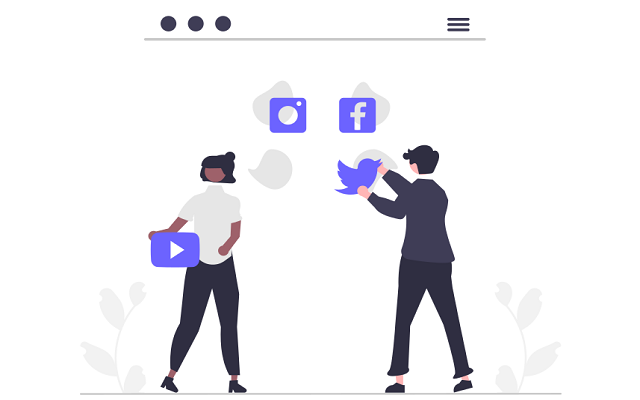
多くの企業がオウンドメディアの運用に取り組んでいますが、効果が出るまでには時間がかかるからこそ、明確な目的とKPIを設定したうえで、戦略的に運用しなければいけません。
目的が明確になれば、オウンドメディアの運用で重要な地道な継続が可能になります。まずは自社の課題を整理し、オウンドメディアが解決に貢献できる課題を明確にしましょう。
参考記事
リスティング広告を世界標準のAIで改善させる
マーケティング活動で重要なリスティング広告。現状実績を改善し、さらに成果を伸ばすことに苦戦しているマーケティング担当者は多いです。弊社ではリスティングAIを活用した、まったく新しいご提案が可能です。
- リスティング広告のコンバージョン数を確実に改善させたい
- 人の手で実績を改善し続けるのが困難
- リスティング広告のプロフェッショナルに課題解決の相談をしたい
こちらから

アドフレックス編集部
アドフレックス・コミュニケーションズ公式アカウントです。
アドフレックス・コミュニケーションズ公式アカウントです。