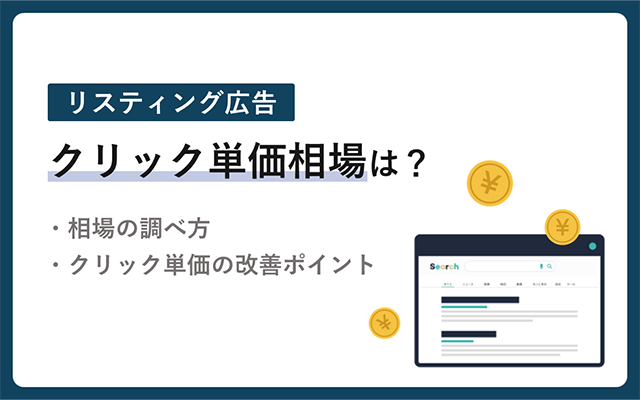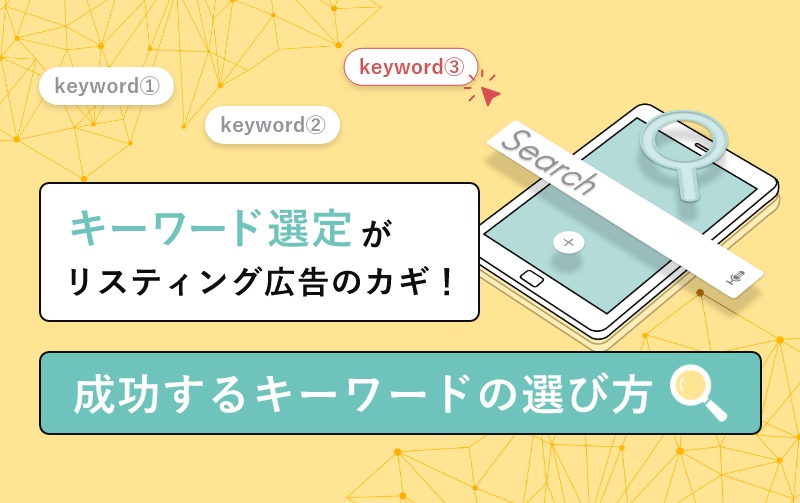広告に求められる新たな役割は、「カテゴライズと多様性の橋渡し」
AIコンサルティングで、コンバージョン数を拡大する
多くのグローバル企業が支持する最先端AIマーケティングソリューション。 各領域に精通したコンサルタントが、貴社の課題に最適なAIツールを選定、事業計画から施策推進までサポートします。
目次
「こうあるべき」という押し付けはよくない。
人それぞれの個性を尊重しよう。
そんな多様性の波が押し寄せるなか、朝日新聞デジタルが、「『for MEN』やめて『2nd』 化粧品にもジェンダーレスの波」と報じた。*1
内容はタイトルどおりで、ロフトはいままで男性用化粧品に「for Men」を入れていたが、ジェンダーレスの海外商品が並び始めたこともあり、昨春から季節に応じて「1st」「2nd」という数字を使い「for Men」という表現はやめたとのこと。
……えっ、わかりづらくない!?
多様性への配慮の結果なのはわかる。
でも「2nd化粧品はこちら」なんて書かれていても、それがなんなのか、まったくピンとこない。
多様性に配慮することでターゲットに届かなくなるのであれば、それはビジネスとして「正しい」といえるのだろうか。
「アジア人向けシャンプー」がほしいけど、そんなもの売ってない
生物として、男性と女性には身体的なちがいがある。
化粧品でいえば、男性の肌質と女性の肌質はちがうし、似合う色もちがうだろう。
男性、女性、それぞれの特徴に合った化粧品を開発するために、日々研究し、努力している人だっている。それを、「多様性」を理由に「ジェンダーレス」にすることが、「ビジネス」として正しいのだろうか。
わたしはドイツに住んでもう8年くらい経つが、ドイツの水には長いこと悩まされた。
水質がちがうからか、髪がいつもパッサパサで、とにかくごっそり髪が抜ける。
いくつかシャンプーを試したが、まとまりが悪く日本のようにサラサラにならない。わたし以外の日本人の友人たちも、同じような悩みを抱えていた。
ドイツの女性は、細くて柔らかい髪質の人が多い。
逆にアジア系の女性は、太くて硬め、まっすぐの髪質の人が多い(ドイツ人の友人からは、「ボリュームがあってゴージャス」とか「まっすぐつやつやしていてうらやましい」なんて言われる)。
だから正直、「男性用化粧品」のように、「アジア人向けシャンプー」なんてのがあったらいいなぁ、と思う。
ただこのご時世、「アジア人向けシャンプー」なんて商品をつくるメーカーはまずないだろう。「アジア人を定義しろ」「アジア人はこういう見た目、と決めつけるな」と即日炎上することが目に見えているから。
でももし、アジア人に多い髪質を生物学的に調べ、それに基づいてシャンプーをつくったとしたら?ターゲットに届くようにアジア人に限定してマーケティングをしたら?
それは、「アジア人の多様性」を否定することになるのだろうか。
「おとう飯」が炎上したのはカテゴライズvs.多様性の構図
ターゲットを明確にして、それを提示したほうが、ビジネスとしては確実にやりやすい。
男性用化粧品なら、男性に多い肌質に即したものを作り、男性が買いやすいパッケージにする。
アジア人向けシャンプーなら、アジア系に多い髪質のケアに適したものにして、話者の人口が多い、たとえば中国語や英語も表記する。
そうすれば、だれに向けたどんな商品かが一目瞭然だし、買う側としても「これは自分にぴったりだ」と手に取りやすいだろう。
でもそのマーケティングは、「決めつけ」のうえで成り立っている。
男性は脂っぽい肌の人が多いだろう、スタイリッシュなデザインのほうが目に留まるだろう。
アジア人なら太くて硬い髪の人が多いだろう、中国語や英語がある程度読めるだろう。
根底には、ターゲットをカテゴリー分けした、いわゆる偏見があるのだ。
だからこういったカテゴライズマーケティングは、「多様性への配慮がない」と批判されることも少なくない。
たとえば数年前、「男飯」という言葉をチラホラ見かけた。いや、もう10年以上も前だろうか。
健康への意識の高さや「料理は女がするもの」という価値観が変わり、家事・育児に積極的な男性がポジティブに評価され、「料理できる男性はステキ」という認識が広がっていった。
そこで、「ふだん料理をしない男性でも作れる、簡単で腹が膨れるレシピ」という意味で、「男飯」という言葉がよく使われていたのだ。
事実、weblioにも「男メシ」という言葉が載っている。*2
そんな流れがあったからか、政府主導でおとう飯(はん)というキャンペーンもスタート。*3
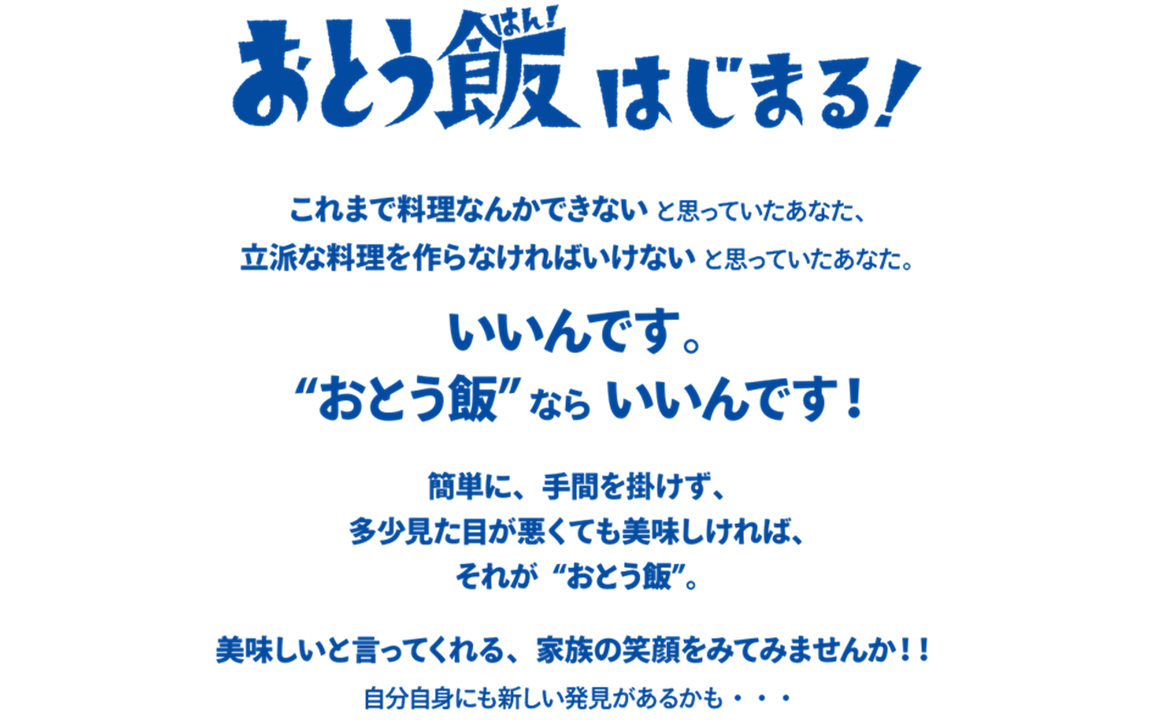
しかしこのキャンペーンには、「長時間労働で料理なんてする時間がない」「おかん飯はちゃんとしてなきゃダメなんですか」といった批判の声が上がり、物議をかもした。
正しい・正しくない、ではなく求められるのは「配慮」
おとう飯キャンペーンのプチ炎上は、「カテゴライズマーケティングvs.多様性」の典型的な構図で、こういったトラブルは最近増えている。
だれがなんと言おうと、統計では、男性より女性の家事負担の割合のほうが大きい。*4*5
だから、「料理しない男性も挑戦してみよう!パートナーの女性はそれを応援してあげてね」というコンセプト自体は悪くないし、特殊な考え方というわけでもない。
でも性別による押し付けが悪だとされる現状、「男は料理しない」「女は料理ができて当然」というカテゴリー分けを前提とした考えは、即座に否定される。「そんなの古い」と。
ほかにも、ファミマの「お母さん食堂」がジェンダーバイアスを助長するとして、名称変更の署名運動が起こり、サジェストワードには「炎上」「フェミニスト」が挙がるようになったこともあった。
これも、「こうあるべき」の押し付けだと言われたわけだ。
ターゲットに届けるために、カテゴライズは便利。
でもそれが、偏見を助長するものだと受け取られたら、すぐに炎上する。
かといって、多様性への配慮を優先しすぎて、本来のターゲットに届かなくなってしまっては無意味。
では、どうすればいいのだろうか。
カテゴライズと多様性の両極をつなぐ素晴らしい広告
そもそも、「カテゴライズ」と「多様性」は両極にある概念であり、相いれるものではないのだ。
でもその2つをつなぐ「橋」があったら……?
そう、その橋になりうるのが、広告じゃないかと思う。
サービス・商品がだれに向けたものなのかがハッキリとわかり、ターゲットに届く。
しかしそこには偏見を助長する意図はなく、多様性にも配慮されている。
そんな広告が打ち出せれば、どうだろう。
たとえば有名な、ゼクシィのこのキャッチコピー。
「結婚しなくても幸せになれるこの時代に、私は、あなたと結婚したいのです」*6
自分の意思で前向きに結婚を選んだ人がターゲットであると明示しつつも、結婚をしない人たちを否定することはしない。
これはまさに、カテゴライズと多様性という、対立する2つの概念をつないだ、名キャッチコピーじゃないだろうか。
ほかにも、たとえばユニクロのエアリズムインナー編の広告。*7
主人公は、女性カップル。
一緒に笑って、出かけて、寝て、抱き合って。
そんな様子とともに、綾瀬はるかさんの「ふたりがしたいことは、みんながふだん着でしていること。ただ、それだけなのだ」というナレーションが入る。
インナーの広告はむずかしく、少し間違えると、「ルッキズム」「性的搾取」と言われかねない(エアリズムはデザイン的にあまり心配ないかもしれないが)。
そんななかで、多様性への理解を示しつつ、ふだんの生活を快適に過ごすアイテムとして、エアリズムをちゃんとアピールしている。とても良い広告だ。
今後広告は、カテゴライズと多様性の橋渡しをすべき
広告は、宣伝をするのはもちろん、企業のブランディングにもよく使われる。
でも広告のちからは、それだけじゃない。いまの時代だからこそ、広告はもっと大きな役割を担える。
カテゴライズマーケティングと多様性への配慮の橋渡しという、大役だ。
どういうターゲットに届けたいかカテゴリー分けし、その層に届ける。しかしそれがあからさますぎると、偏見の助長と受け取られ、共感は得られない。
だからこそ、ターゲットに届けたうえで、なおかつ多様性を否定する意図はないことを丁寧に伝えるような広告が、いまの時代には必要なのだ。
それがなければ、決めつけから炎上したり、逆に「すべての人に」とコンセプトがおおざっぱすぎてコア層に届かなかったりしてしまう。
今後広告は、ターゲットに刺さる矛になり、多様性への配慮という盾にもなってくれるだろう。
その視点でどういう広告が効果的かを考えれば、きっと「いまの時代に合った広告」が完成するんじゃないだろうか。
【参考資料】
*1 朝日新聞DIGITAL「『for MEN』やめて『2nd』」 化粧品にもジェンダーレスの波」
*4 男女共同参画局「男女共同参画白書(概要版)平成30年版
*6 maidigitv 「佐久間由衣、ゼクシィ10代目CMガールに またも朝ドラ女優抜てき」
*7 oricon「綾瀬はるかx桑田佳祐、ユニクロCMシリーズ第5弾!綾瀬がお花屋さんに 『ふだん着の日が、人生になる。』「エアリズム インナー 篇」」
メールマガジンを購読する
マーケターや広告担当者向けに、リスティング広告を中心としたマーケティングに役立つ情報を無料でお届けします。
(購読解除はいつでも可能です)
メールマガジンを購読する
マーケターや広告担当者向けに、リスティング広告を中心としたマーケティングに役立つ情報を無料でお届けします。無料で登録する
(購読解除はいつでも可能です)
AIコンサルティングで、コンバージョン数を拡大する
多くのグローバル企業が支持する最先端AIマーケティングソリューション。 各領域に精通したコンサルタントが、貴社の課題に最適なAIツールを選定、事業計画から施策推進までサポートします。

アドフレックス編集部
アドフレックス・コミュニケーションズ公式アカウントです。
アドフレックス・コミュニケーションズ公式アカウントです。