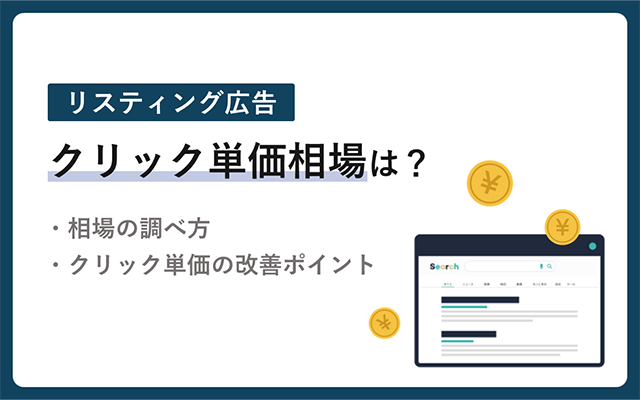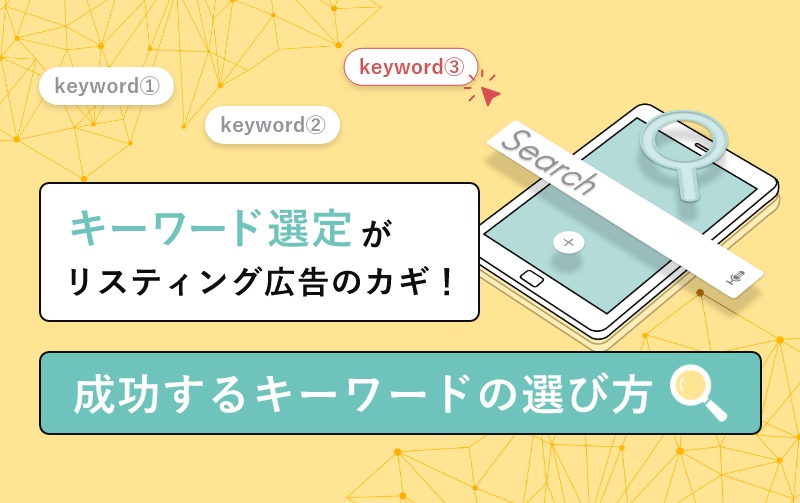BtoCマーケティングとは?施策の選び方や成果を出すポイントまで解説

- 「BtoCマーケティングの担当になったけれど、なにから手をつければいいか分からない」
- 「どの施策が自社にあっているのか分からない」
このような、悩みはありませんか?
社内に頼れるマーケターが在籍していないケースやBtoCマーケのノウハウが蓄積されていないケースでは、現場から上記のような悲鳴も聞かれています。
また、やみくもに施策を展開しても、貴重な予算だけが消化してしまい得策とは言えません。
そこで本記事では、BtoCマーケティングに精通している弊社が、BtoCマーケティングの特徴や主な施策と向いているターゲット、成功ポイント、事例まで解説します。
本記事を参考に、自社に最適な施策を推進していただければと思います。
BtoCマーケティングの施策選択でお困りではありませんか?
10年以上の広告運用ノウハウを保有するアドフレックスでは、BtoCマーケティングにおいて貴社の費用対効果を考慮したご提案が可能です。
特に顕在ニーズが明確な見込み顧客に対して、AI(自動化)とヒト(コンサルティング)を活用した広告運用による事業拡大を得意としております。
- 自社商材に最適なBtoCマーケティングの施策選択に困っている
- 見込み顧客の顕在ニーズを確実に獲得したい!SEOそれともリスティング?
- リスティング広告は時代遅れ?費用対効果を高める運用法について知りたい
こちらから
目次
1.BtoCマーケティングとは?
BtoC(Business to Consumer)とは:
企業が一般消費者に商品やサービスを提供するビジネス。
BtoCマーケティングとは、企業が一般消費者に向けて製品やサービスを売るための、一連のマーケティング活動のことです。
BtoCマーケティングの特徴としては、「ターゲットが個人の消費者」「商材単価が比較的低い」「タッチポイントが多様」など、複数の傾向が挙げられます。
それに対して、BtoB(Business to Business)とは、企業対企業で行われる取引のことです。
2.BtoCとBtoBマーケティングの違い

BtoCマーケティングの理解を深めるために、BtoBマーケティングとの違いを詳しく見ていきましょう。
2-1.対象者
BtoCマーケティングは、個人消費者または世帯をターゲットとしています。
消費者のニーズや好みなどに対応しなければならない。
一方、BtoBマーケティングは企業や組織を対象にしています。
ターゲットは、マネージャーや役員など企業の意思決定者で構成されており、自社商材がどのようにビジネス上の課題を解決するかを訴求する必要があります。
2-2.購買行動
BtoCマーケティングでは、個人の好みや感情によって購入の意思決定が行われることが多い状況です。
特に、スマートフォンの普及により、衝動買いをする消費者が増加しています。
Googleは、スマホで検索し、衝動的に購入する行動を「パルス型消費行動」と提唱しています。

出典:データから見えた「パルス型」消費行動ーー瞬間的な購買行動が増えている:買いたくなるを引き出すために:パルス消費を捉えるヒント(2)|Think with Google
上記画像においては、左側が通常の認知から購買までにおける購買意欲の推移であり、右側がパルス型消費行動です。
比較すると分かるように、パルス型消費行動は購買意欲が急激に高まっています。
また、近年個人消費者の意思決定サイクルは短い傾向にあり、ブランドの評判や広告・価格・利便性などの要素が購買意欲に影響を与えています。
一方、BtoBの購買行動は、より合理的で複雑です。
ガートナー社によれば、BtoBの意思決定には平均6~10名が関与すると報告されています。BtoBにおいては、複数の意思決定者が関与し、高額な商材を取り扱うため、意思決定サイクルが比較的長い傾向にあります。
また、価値提供や投資収益率(ROI)、長期的な利益などが購買の判断材料につながるのも特徴です。
2-3.価格
一般的に、BtoCの製品やサービスはBtoB製品よりも低価格です。
BtoCマーケティングにおける価格戦略は、より多くの消費者にアピールするためにあり、競争力のある価格を設定することが多いでしょう。
価格は重要な購買要素のため、割引やお得なプロモーションなどの訴求が効果的。
BtoB商材の価格はBtoCよりも高額で、数百万円を超えることも珍しくありません。
価格も重要な購買要素ですが、それよりも提供価値やサポート制度などが重視される傾向にあります。
2-4.マーケティングチャネル
BtoCマーケティングは、Web広告・SNS・インフルエンサーの起用など、多様なチャネルで消費者との接点を作ります。
それに対しBtoBマーケティングでは、業界専門誌・展示会・パートナー企業など、よりターゲットを絞り込んだチャネルを活用することが多い状況です。
2-5.ブランディング
BtoBとBtoCともにブランディングは重要ですが、そのアプローチ手法は異なります。
BtoCマーケティングでは、ストーリーを用いながらターゲットと感情的なつながりを作り、消費者のブランドロイヤルリティを高めるのが特徴。
一方、BtoBマーケティングでは、データ駆動型アプローチにより信頼性や信用、専門性を確立することに重点を置いています。
3.BtoCマーケティングのメリット

効果的なBtoCマーケティングを実施するためにも、メリットを理解しておきましょう。
BtoCマーケティングには、以下4つのメリットがあります。
- ターゲット市場が大きい
- 感情に訴えられる
- SNSマーケティングとの親和性が高い
- 売り上げにつながるのが速い
メリットの詳細を見ていきましょう。
3-1.ターゲット市場が大きい
取り扱い商材にもよりますが、BtoCマーケティングは幅広い消費者をターゲットにするため、BtoBよりも市場が大きい傾向にあります。
経済産業省の調査によれば、2021年の物販系分野の国内BtoC – EC市場規模は、前年比8.61%増の13兆2,865億円です。
BtoC市場は広いため、大きなリーチと売り上げが期待できる。
参考:令和3年度 電子商取引に関する市場調査 報告書|経済産業省 商務情報政策局 情報経済課
3-2.感情に訴えられる
BtoCマーケティングでは、消費者の感情や好みに訴えるマーケティングが可能です。
マーケティング担当者は、消費者の行動や心理を理解することで、消費者の感情に響く魅力的な物語や体験を作り出し、ブランドとの結びつきやロイヤルティを高められます。
海外の著名なマーケターであるレス・ビネ氏とピーター・フィールド氏の調査によれば、感情に訴える広告キャンペーンが最も効果的で、長期的に普及率や売り上げ、市場シェアを高めると報告されています。
BtoCマーケティングの推進においては、感情に訴えかけることを意識するとよいでしょう。
3-3.SNSマーケティングとの親和性が高い
Twitter・Instagram・TikTok・YouTubeなどを活用したSNSマーケティングとBtoCの相性は非常によく、マーケティング施策を展開する上でも重要視されています。
先にご紹介したパルス型消費行動が示すように、消費者はスマホで商品を発見し、急激に購買意欲が高まり、購入に至ります。
一方でBtoB商材の場合は高単価のため、パルス型消費は発生しにくい状況です。(単価の低いBtoC商材ならパルス型消費に期待できます。)
多くのSNSで自社商材を魅力的に訴求すれば、認知度拡大やブランディング、衝動買いなどにつながるでしょう。
3-4.売り上げにつながるのが速い
BtoBと比べると、低単価のBtoC商材の意思決定サイクルは非常に短い傾向があります。
適切なマーケティング施策を展開すれば、即座に収益をあげられるでしょう。
そのためにも、効果的なプロモーションや特別オファー、分かりやすいCTAなど消費者に直接購入を促す仕掛けが必要。
4.BtoCマーケティングのデメリット
BtoCマーケティングのデメリットも併せて理解すれば、潜在的なリスクや障壁を考慮したうえで、施策を推進できるようになります。
BtoCマーケティングのデメリットは以下の通りです。
- 競争が激しい
- 価格への敏感さ
- LTVが短い
ここからは、各デメリットの詳細を解説します。
4-1.競争が激しい
BtoC企業は競争が激しい市場です。例えば、化粧品産業は1,000社以上のメーカーがあると言われています。
多くの競合がひしめくなか、自社ブランドを選んでもらうためにも、差別化を図るマーケティング施策が求められます。
4-2.価格への敏感さ
BtoCの消費者は料金に敏感であることが多く、価格が最重要課題になることが多々あります。あなたも同じような商材を選ぶとき、価格の安いほうを優先した経験があるのではないでしょうか。
資金やリソースに限りがある中小企業の場合、どうしても価格競争では大企業に負けてしまう可能性が高い状況です。
だからこそ、マーケティング施策でブランディングや想起率の向上、共感の醸成などを図り、自社ブランドを選んでもらわなければいけません。
4-3.LTVが短い
LTV(Life Time Value)とは、顧客生涯価値を意味し、1人の顧客が自社と取引を開始してから終了するまでにもたらす利益を測る指標のことです。
多くのBtoC業界では、顧客ロイヤルティやリピート購入は比較的低い傾向にあります。
また、消費者は好みや経済状況の変化、競合キャンペーンによって、ブランドを頻繁に変更することもあるのです。
そのため、BtoCマーケティングにおいては既存顧客の維持だけではなく、新規顧客を獲得するための継続的な努力が必要となります。
5.BtoCマーケティングの施策一覧

BtoCで活用できる主なマーケティング手法は、以下の5つです。
- SNSマーケティング
- SEOマーケティング
- Web広告
- インフルエンサーマーケティング
- MA(マーケティングオートメーション)
5-1.SNSマーケティング
SNSマーケティングとは、TwitterやFacebookなどのSNS上でコンテンツを投稿し、商材の宣伝やブランディング、顧客とのコミュニケーションを展開する手法のことです。
潜在層から顕在層、既存顧客まであらゆるターゲットにリーチできます。幅広いユーザーにアプローチできる点を踏まえると、潜在層との接点を構築し、売り上げへとつなげる施策に有効です。
SNSマーケティングを推進する際は、自社商材やターゲットに適したプラットフォームを選ばなければいけません。
例えば、10代や20代の女性を対象にした美容商材はInstagram、季節やトレンド性の高い商材はTwitterが向いています。
活用例としては、自社アカウントの運用や期間限定キャンペーンの展開などが挙げられるでしょう。
興味を持ったユーザーが情報をシェアすれば、二次的な宣伝効果も期待できる。
5-2.SEOマーケティング
SEOマーケティングとは:
検索意図とユーザーニーズに合致した情報を提供していく手法。
SEOマーケティングを推進すれば、GoogleやYahoo!などの検索結果画面に自社サイトを表示できます。
BACKLINKOが400万ものGoogle検索結果画面を調査した結果、1位に表示されたサイトの平均クリック率は27.6%とのことです。
例えば、「月間検索ボリューム:3,000」のキーワードで1位を獲得できれば、826件の流入が見込めます。
ユーザーの課題やお悩み解決コンテンツを作成し、検索結果の上位に表示することで、広告費をかけなくてもアクセス数の増加が期待できる。
ただし、一時的な情報提供では購買につながりにくいため、定期的に情報を発信してユーザーとの関係を維持することが大切です。SEOマーケティングは、対象とするターゲットがインターネット検索で情報収集をしやすい商材に向いています。
例えば、アパレル・美容品・家電製品・金融商品・オンライン英会話・家具などです。
それに対して、日用品などのオンライン検索で接点を持たない商材は、マスメディア広告やSNSマーケティングなどが向いています。
なお、SEOマーケティングに似た言葉に「コンテンツマーケティング」がありますが、これはコンテンツを使ったマーケティングの総称です。コンテンツSEOもSNSマーケティングも、コンテンツマーケティングに含まれます。

5-3.Web広告
Web広告とは、その名の通りインターネット上に配信する広告のことです。
代表的なWeb広告は、以下の通りです。
- 検索結果画面の上部・下部に配信する「リスティング広告」
- Webサイトの配信枠にバナーなどを配信する「ディスプレイ広告」
- 動画コンテンツの途中に配信する「動画広告」
Web広告の特徴は、高精度のターゲティング機能によりユーザーにピンポイントでアプローチできる点ではないでしょうか。
また、成果が出た際にのみ費用が発生するため、費用対効果が極めて高いのも特徴の一つです。数百円から広告を配信できるので、予算の少ない企業でも取り組みやすいでしょう。
これからBtoCマーケティングに取り組む場合は、リスティング広告のご利用を検討してみてください。リスティング広告は顕在層にリーチできる性質上、早い段階で成果の創出を見込めます。
一方、ディスプレイ広告は潜在層にリーチするため、認知拡大やブランディングに有効です。短期的な成果にはつながらないため、初めにディスプレイ広告に取り組むと、社内の協力を得られない可能性があります。
また、広告を配信すれば思い通りの効果がすぐに出る、というわけではありません。
目標に見合った成果を上げて費用対効果を高めるには、出稿先や入札額の調整、適切なクリエイティブの制作などを含めた総合的な戦略の立案が求められます。
5-4.インフルエンサーマーケティング
インフルエンサーマーケティングとは:
ターゲット層に人気の高いインフルエンサーを起用してPRする方法のこと。
SNSを活用した施策が代表的です。ほかの手法よりもユーザー目線で製品を紹介できるのが、インフルエンサーマーケティングの魅力ではないでしょうか。
インフルエンサーが抱える膨大なフォロワーにアプローチできるため、商材の認知度が低かったり、多くの潜在層と接点の構築をしたりする場合に有効です。
数あるインフルエンサーのなかでも、YouTuberやTikTokerの影響力はいまや無視することはできません。株式会社AtoOneが、YouTubeもしくはTikTokを運用している企業担当者に調査した内容によれば、94.4%が「インフルエンサーとのコラボで効果を実感した」と回答しています。
YouTubeとTikTokは、映像と音で商材を訴求できるため、深い商材理解の促進や購買意欲の醸成ができることなどが理由に挙げられるでしょう。
インフルエンサーが抱えるフォロワー数や知名度によって異なりますが、大手メディアへの広告掲載よりも、大幅にコストを抑えられるメリットもあります。
5-5.MA(マーケティングオートメーション)
MA(マーケティングオートメーション)とは:
マーケティング活動を自動化して収益の最大化を図るためのツール。
MAツールを使えば、リードの分析や一元管理、購買確度の高いリードの選別などを自動化できます。
顧客が必要な情報を最適なタイミングで届けられるため、ナーチャリングや顧客満足度の向上、アップセル/クロスセル数の増加などを見込めます。
しかし、「他社が導入しているから」「流行だから」などの理由でMAツールを導入しても、十分な活用は困難です。
基本的に、毎月のリード獲得件数が数百件以上ある、かつ、コンテンツを量産できる体制がある場合にのみMAツールの導入を検討しましょう。
6.BtoCマーケティングの担当者なら覚えておきたい顧客の意思決定プロセス
BtoCマーケティング担当者が身につけておきたいのが、見込み顧客の「意思決定プロセス」に関する知識です。
6-1.AIDMA
AIDMA(アイドマ)は、ネットが普及する前から用いられているフレームワークです。
ユーザーの意思決定プロセスを5つに分解して、認知から購買行動に至るまでの流れを表しています。

古くから使われているモデルのため、現代の購買プロセスに即していない部分もありますが、マーケティングの基礎知識として身につけておきたいところです。
6-2.AISAS
AISAS(アイサス)は、SNSの情報拡散も考慮しているフレームワークです。

企業から消費者へのワンウェイモデルとなっていたAIDMAと異なり、消費者の能動的な行動である「Search」と「Share」を加えたインタラクティブなモデルへと進化しています。
6-3.DECAX
DECAX(デキャックス)は、近年のコンテンツマーケティングに対応したフレームワークです。
AIDMAとAISASは視点が企業側にありますが、DECAXはユーザー視点の購買行動モデルとなっています。

「Discovery(発見)」がプロセスに含まれているため、PULL型を主体としたBtoCマーケティングの戦略立案にも役立つでしょう。
7.BtoCマーケティングを成功させるためのポイント

BtoCマーケティングを成功させるためのポイントは以下の3つです。
- 顧客理解を深める
- リスティング広告を出稿する
- 潜在層の拡大を意識する
それぞれのポイントを見ていきましょう。
7-1.顧客理解を深める
BtoCマーケティングに取り組む前には、顧客理解を徹底的に深めましょう。インターネットが発展した現代においては、消費者は能動的に情報収集できるようになりました。
一方で、顧客は広告やSNS、メールなどで毎日膨大な情報に触れるようになったため、情報の取捨選択をしています。自社の情報を見てもらうためにも、顧客にとって価値あるコンテンツを提供しなければいけません。
そのためにも、「顧客はどのような課題を抱えているのか」「顧客の購買動機は」などの問いに回答して、顧客理解を深め、コンテンツに落とし込む必要があるのです。
顧客理解を深めるためには、ペルソナとカスタマージャーニーマップの作成が有効。
ペルソナとは、商材の理想もしくは典型的なユーザー像のことであり、デモグラフィックとサイコグラフィックを設定し、一人の人物をイメージできるまで詳細に設定します。
その後、カスタマージャーニーマップを作成すれば、認知から購買に至るまでのペルソナの悩みや心理、接点などを可視化できるため自社に最適な施策の選定が可能です。
7-2.リスティング広告を出稿する
これからBtoCマーケティングに取り組む場合、リスティング広告の出稿を検討してみてください。
まだマーケティングに取り組んでいない、もしくはマーケティングに取り組み始めたばかりという場合は、社内にマーケティングの文化がないと思われます。マーケティングの文化がなければ、十分な予算や人員を確保するのは困難でしょう。
これから取り組む場合は、初めての成功体験が重要です。成功体験さえ得られれば、他部門や経営陣の協力を得られます。
なお、短期間で成果を挙げられる施策の一つに、リスティング広告が挙げられます。リスティング広告は、課題や悩みの解決策を探す検索ユーザーにアプローチできるため、短期間での売り上げ向上も期待できるでしょう。
また、低コストで出稿でき、成果が出たときにだけ費用が発生する点も、予算の限られた企業には魅力的なはずです。
一方、オウンドメディアやSEO、SNS運用などは成果が出るまでに一定の期間がかかるため、初期の施策にはおすすめしません。
リスティング広告の運用やノウハウに自信がない場合には、弊社ソリューションの一つである「Optmyzr(オプティマイザー)」がおすすめです。

Optmyzrは、Googleの元エバンジェリストが開発した広告運用自動化ツールであり、リスティング広告で安定した成果を見込めるよう、以下のサポートをいたします。
- 24時間365日モニタリングし急激な数値変動を適宜アラート
- スキルやノウハウに依存しないAI分析データによるインサイトをご提案
- 新規キーワードの追加提案および無駄なキーワードの除外提案
- 高額なCPAキーワードの入札調整 など
リスティング広告の運用歴やノウハウが少ない企業でも、AIによる改善提案により、安定した成果を見込めます。
Optmyzrのサービスや特徴を詳しく知りたい方は、資料を無料でプレゼントいたします。
資料の概要
- Optmyzr(オプティマイザー)とは
- 機能紹介
- 24時間365日の入札調整など
7-3.潜在層の拡大を意識する
BtoCの顧客はLTVが短い傾向にあるため、潜在層の拡大を意識的に行う必要があります。
リスティング広告で成果が出始めたら、ディスプレイ広告やSNS広告、SNSマーケティングなどにも取り組んでみましょう。
特に、Webサイトやアプリの広告枠に画像や動画を配信するディスプレイ広告は、潜在層の拡大に有効な施策となる。
ディスプレイ広告を使えば、広告をクリックされなくとも、何度も表示することで顧客の記憶に残ります。
Yahoo! JAPANの調査によれば、第一想起率が高いほどブランドやサービスの検討者数も増加するとの結果が発表されています。

出典: よく分かる「第一想起」〜Yahoo! JAPAN第一想起分析|Yahoo! JAPAN
例えば、あなたも同ジャンルの製品を購入する際、親しみのあるブランドを選んだ経験があるのではないでしょうか。
このようにディスプレイ広告やSNS広告で、ユーザーとの接触回数を増やせば、第一想起率が高まり、結果的に売り上げへとつながるのです。
売り上げ拡大のためにも、潜在層の拡大を目標にした施策に取り組みましょう。
8.BtoC向けWebマーケティングの注意点

BtoC向けにWebマーケティングを展開するにあたって、以下の3点に注意する必要があります。
- ユーザーニーズを把握する
- 目的に応じた手法を選択する
- 炎上リスクを考慮する
8-1.ユーザーニーズを把握する
まずは、ユーザーニーズを把握することから進めましょう。かつては自社目線で製品をアピールするPUSH型が主流でしたが、現在はユーザーのニーズに沿うことを重視します。
施策の展開にあたっては、ユーザーに自社製品を「見つけてもらう」ことをイメージすることが重要です。
8-2.目的に応じた手法を選択する
マーケティングの手法によっては、成果が出るまでに時間がかかるものもあります。
例えば、コンテンツSEOは、効果が出るまで半年から1年の期間を要するでしょう。
長期的な視点で取り組むのであれば問題ありませんが、即効性を求めるならWeb広告やインフルエンサーマーケティングの活用が有効です。
8-3.炎上リスクを考慮する
個人を対象としたBtoCは、拡散性の高いSNSマーケティングとの親和性が高い傾向にあります。
一方で、トラブルが起きた場合にすぐに拡散されてしまうリスクもあります。
ネガティブな評判はすぐに修復するのが難しく、長期にわたることも少なくありません。
ユーザーとコミュニケーションを図るには、発信する内容に十分注意してください。
9.BtoCマーケティングを成功に導いた企業事例
ここからは、BtoCマーケティングを成功に導いた企業事例をご紹介します。
9-1.ベルリッツジャパン株式会社|バズ部事例

出典:ベルリッツ ブログ
株式会社ルーシーが運営する、コンテンツマーケティング・SEOを中心としたデジタルマーケティング情報サイト「バズ部」の事例です。
ベルリッツジャパン株式会社は、ビジネス向け英会話を提供する企業です。同社は、オンライン英会話市場に多くの競合が参入していたため、リスティング広告からの獲得単価が悪化している課題を抱えていました。
そこで、大きな費用をかけずにスタートできるコンテンツマーケティングに取り組みます。同社が意識していたのは、ユーザーの悩みを120%解決するコンテンツ制作です。
週に1回のペースで、キーワードからユーザーの検索意図をくみ取り、ユーザーが満足するコンテンツ制作を実施しています。
この施策を継続した結果、2016年の月間PV数65万、ブログを起点とした問い合わせ数200件/月を達成したのです。
この事例から学べるのは、SEOやWeb広告、SNSなどのコンテンツマーケティングに取り組む際は、徹底的にユーザー目線になること。
また、週に1回の投稿でも長期にわたって継続すれば、大きな成果を創出できることが理解できます。
参考:週に1記事の更新で月間65万PV、月間200件超のお問い合わせを獲得するベルリッツブログ|バズ部
9-2.株式会社日比谷花壇様|Optmyzr(オプティマイザー)導入事例

弊社、ソリューションの一つである「Optmyzr(オプティマイザー)」の導入事例です。
株式会社日比谷花壇様は、「感動はいつも 花とともに」をキーメッセージに、店舗の全国展開やECなど、多岐にわたるフラワー事業を展開しています。同社は、新型コロナウイルス感染症の影響で激化するEC事業に対応するため、リスティング広告を強化します。
具体的には、リスティング広告自動運用化ツール「Optmyzr」を導入しました。Optmyzrには、キーワードや入札単価の最適化、広告文パフォーマンスの可視化など、さまざまな機能が搭載されています。
そのなかでも、同社が特に重宝したのがルールエンジン機能です。ルールエンジン機能により、指名キーワードや非指名キーワードなどキーワードの特性によって、入札に強弱をつけるなど最適な戦略が可能になりました。
つまり、従来の媒体が持つ自動最適化機能よりも、きめ細やかな運用ができるようになったのです。
結果、CPAを目標圏内に抑えながらCV獲得数83.5%上昇という成功を達成しています。
参考:【導入事例】株式会社日比谷花壇様、リスティング広告最適化AI「Optmyzr(オプティマイザー)」でCV83%アップ!|OPTMYZR
10.BtoCマーケティングを加速するためのおすすめ本3選
最後にBtoCマーケティングに取り組む上で、役立つ本を3選ご紹介します。
10-1.USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入門

出典:KADOKAWA
本書の著者は日本を代表するマーケターの森岡 毅氏。窮地にあったUSJを、森岡氏がどのように復活させ、2015年10月には東京ディズニーランドを超えるほどの集客数を誇る、テーマパークになれたのかが解説されています。
本書は、これからBtoCマーケティングに取り組む方にこそおすすめしたい一冊です。マーケティングのテクニックというよりも、本質的な考えについて書かれているのが特徴です。
例えば、本記事のなかでも繰り返しお伝えした顧客視点の重要性が記されています。森岡氏は、USJのV字回復の原動力として、USJが消費者視点の企業になったからだと述べています。
そのほかにも、以下の内容を学べるのが特徴です。
- 組織におけるマーケティングの立ち位置
- マーケティングの定義
- 技術とマーケティングの関係性
マーケティングに取り組むなかで、何度も読み返すことになるであろう名著です。
10-2.たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング

出典:翔泳社
本記事では、顧客視点や顧客課題の特定が重要だということを繰り返し述べました。それでは、どのように顧客視点の施策を推進すればよいのでしょうか。その答えは、本書にあります。
著者の西口氏は、P&Gのブランドマネージャーやマーケティングディレクター、スマートニュース執行役員などを務めた著名なマーケターです。西口氏は本書のなかで、たった1人の顧客の意見を聞く「N1分析」を推奨しています。
一人の顧客がロイヤル顧客になったきっかけを理解すれば、ロイヤル化していない顧客にも同じきっかけを提供することで、ロイヤル化を促せるためです。西口氏の経験やケーススタディを絡めながら、N1分析の方法が分かりやすく解説されています。
顧客理解を深めたい方や顧客視点に立ったマーケティングをしたい方におすすめ。
10-3.僕らはSNSでモノを買う 僕らはSNSでものを買う
BtoCマーケティングとSNSの親和性は高いですが、なぜSNSで商材が売れるのか、どうすれば情報を届けられるのかなどを理解しなければ、期待した成果は見込めません。
SNSマーケティング入門者におすすめしたいのが、「僕らはSNSでモノを買う 僕らはSNSでものを買う」です。本書では、ユーザーが投稿するコンテンツ「UGC」とSNS時代の新たな購買プロセス「ULSSAS」を中心に解説しています。
対話形式で進められ、事例も豊富なので、非常に読みやすいのが特徴。
SNSマーケティングに取り組む方は、まずは本書を読んでみるとよいでしょう。
11.まとめ
BtoCマーケティングにおいては、いかに多くの消費者と接点を構築し、短期間で購買意欲を高められるかが成果を出すカギとなります。
数ある施策のなかでも、リスティング広告とディスプレイ広告、およびSNSマーケティングは特に有効です。
まずは顧客の課題や悩みを理解し、それを解決するコンテンツを提供するようにしましょう。
BtoCマーケティングの施策選択でお困りではありませんか?
10年以上の広告運用ノウハウを保有するアドフレックスでは、BtoCマーケティングにおいて貴社の費用対効果を考慮したご提案が可能です。
特に顕在ニーズが明確な見込み顧客に対して、AI(自動化)とヒト(コンサルティング)を活用した広告運用による事業拡大を得意としております。
- 自社商材に最適なBtoCマーケティングの施策選択に困っている
- 見込み顧客の顕在ニーズを確実に獲得したい!SEOそれともリスティング?
- リスティング広告は時代遅れ?費用対効果を高める運用法について知りたい
こちらから

アドフレックス編集部
アドフレックス・コミュニケーションズ公式アカウントです。
アドフレックス・コミュニケーションズ公式アカウントです。